![【ロシア訪問記】ロシア極東タイガの森を行く ~森の民ウデへ族を訪ねて~]() 取材・写真・文/大草芳江
取材・写真・文/大草芳江
2012年12月17日公開
日本のすぐ隣に「極東のアマゾン」
ロシア極東ビキン川流域に広がる原生の森、通称「極東のアマゾン」を、東北大学生態適応グローバルCOE国際フィールド実習のレポーターの仕事で、9月下旬に訪れた。
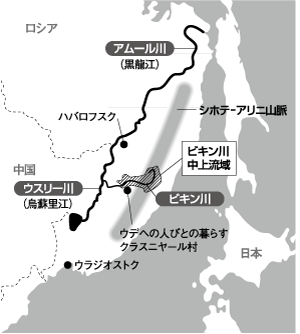
【図】ロシア極東ビキン川中上流域に位置するクラスニヤール村(資料提供:タイガの森フォーラム)
隣国でありながら、つながりを実感しにくい、「近くて遠い国」ロシア。しかし、日本海を挟んで日本列島のすぐ対岸を流れるアムール川の支流・ビキン川流域には、針葉樹と広葉樹が混交する「ウスリータイガ」と呼ばれる貴重な原生の森が広がり、後述するように日本とも関係があるという。
さらに、この森の恵みはビキン川からアムール川へ流れ、アムール川はオホーツク海に注ぎ、親潮の生産性にも深く関係することが、近年明らかになってきた。つまり三陸沖の漁場の豊かさとも、タイガの森はつながっているのだ。
その森は、絶滅危惧種アムールトラを頂点とした生物多様性の宝庫であると同時に、自然の恵みを巧みに利用してきたウデへら、少数先住民族たちの生活の場でもある。今なお伝統的な狩猟採集生活を営むという、「森の民」ウデへ最大の集落・クラスニヤール(Krasny Yar)村を訪れた。
※公式レポートは、東北大学生態適応GCOEの報告ページをご覧ください。
クラスニヤール村にあるものとないもの

【写真1】クラスニヤール村
ビキン川中流域に位置するクラスニヤール村へは、ハバロフスク経由で行く。成田からわずか約2時間のフライトでヨーロッパ風な街並み広がるハバロフスクに到着。そしてハバロフスクから南へ約210km、凸凹の悪路を車で行くこと約8時間で、人里離れたクラスニヤール村に到着した。
クラスニヤール村の人口は700人弱。その大半がウデヘだ。他にナナイ、ウリチなどのツングース系民族や、ロシア系も住む多民族村だが、母国語をロシア語とし、民族間の混血も多く見られる。学校や売店、病院や郵便局はあるが、警察はない。

【写真2】ホームステイ先の食卓
ホームステイ先の食卓には、タイガで獲れたシカやイノシシの肉、キノコや薬草、ビキン川で釣れたサケやイトウなどの魚のほか、庭の畑で穫れたジャガイモやトマトなどの野菜がバラエティ豊かに並ぶ。香草の効かせ方も巧く、素材の旨みが際立ち、実に美味い。
風呂はないが、ロシア式スチームサウナ「バーニャ」で汚れと疲れを落とす。上水道はないので、井戸水を使い、薪で湯を沸かす。未舗装の道路は凸凹だが、牛がのんびりと歩き、すれちがう村人たちが「ズドラーストヴィチェ!(こんにちは)」と手を振る。村に3つしかないディーゼル発電機による電力供給は不安定だが、次第に暗さと不便さに慣れていった。

【写真3】バースデーパーティーのようす
ある日、ホームステイ先のお母さんが朝からお洒落に着飾っていた。辞書片手に理由を尋ねると、今日はお母さんの誕生日らしい。ハンターのお父さんが獲ったアカシカが解体され、肉が団子やスープに変わっていく。今日はご馳走だ。その様子を犬が物欲しそうに眺めていた。
日が落ちる頃、村中から親戚や友人たちが、村では手に入らないであろう酒片手にぞくぞくと集まった。ウォッカやシャンパンで乾杯し、ご馳走を囲み、お母さんは皆にハグされながら祝福されていく。最後は、灯篭に火をつけて、空へ飛ばす風習があるようだ。満天の星空も祝福しているような、そんな幸せに満ちた時間がゆっくりと流れていた。

【写真4】街のあちこちで遭遇するゴミの山
一方で、急激な近代化に伴い発生する公害問題が、この村でも例外なく起こっていた。プラスチックやビニールゴミが急増したが、人々は生ゴミを捨てていた昔と同じ感覚で無造作に廃棄するため、村のあちこちでゴミの山に遭遇した。バーニャでそのまま垂れ流すシャンプーや洗剤も、自然の自浄作用を超える量ではないかと懸念された。
また、「伝統的な狩猟採集生活を営む少数先住民族」と聞いて勝手に抱いていたイメージとは裏腹に、テレビや冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品の普及も想像以上に進んでいた。自称「ゲーマー」でプレステを所有するというハンターの子どもにも出会った。
近代化によって、少数先住民族と自然との関係性は、希薄化してはいないのだろうか。もしそうならば、この貴重な森も、いずれは消えてしまうのではなかろうか。実は個人的にそんな疑いを持ちながら、ハンターたちと一緒に、ハンティングテリトリー内のタイガへ入ったのである。
ハンターたちと一緒にタイガの森へ

【写真5】ビキン川を原動付小舟で遡る
ハンターたちの猟師小屋があるウリマ山基地までは、村からおよそ60km。ビキン川を原動付小舟で約4時間かけて遡って行く。道中「神様の山」で船を止める。森や川に宿る霊魂たちに狩りの安全と成功を祈願するためだ。自然界の霊魂と人間界をつなぐ、ここは、シャーマニズム発祥の地でもある。ただ近年は、神様の山で止まらずに、ウリマ山へ直接むかうハンターが大半という。
秋めき始めたウリマ山が見えた。ここビキン川流域には、針葉樹と落葉広葉樹が混交する手付かずの森が広がり、アカシカやイノシシ、アムールトラのほか、ユーラシアカワウソやシマフクロウなどが生息している。

【写真6】ハンティングテリトリーのウリマ山をハンターの案内で歩く
タイガをハンターの案内で歩いた。この森で獲れるクロテンなどの毛皮獣は、今なお村の主力産品だ。クロテンを傷つけずに捕るための伝統的な罠猟をいくつか教えてもらった。獣に勘付かれぬよう罠を仕掛けた丸太橋に苔を生やすなど、他にも様々な工夫があるそうで、技術のバラエティ豊かさに伝統の重みを感じる。
16世紀、ロシア人が広大なシベリアへの領土拡張を始めた大きな誘因となったのは、当時、ロシアの貴重な外貨獲得手段であったクロテンなど高級毛皮の獲得だった。狩りの技術に優れていた先住民族ウデへの人々にとっては、このクロテンの毛皮がお金にもなり、税金にもなり、供物にもなった。
ソ連時代は、国営狩猟組合へ毛皮を売って生活した。そして社会主義体制崩壊後の今、旧ソ連時代は国家によって確保されていた販売ルートが閉ざされ、自力販売が求められるようになっている。

【写真7】チョウセンゴヨウ
森では今や希少種というチョウセンゴヨウ(マツの一種)を幾つも見た。ウデへの人々は、生活の基盤としてチョウセンゴヨウを残そうとしているという。その実を食物とするリスなどの草食動物、その草食動物を捕食するクロテンやアカシカなどの数に影響するためだ。
一方、チョウセンゴヨウは木材としての価値も高い樹木である。そのためロシア沿海地方のチョウセンゴヨウは、日本を始めとする周辺国に輸出するために旧ソ連によって伐採され、20世紀後半の50年間で約50%減少したという。戦後から日本の多くの木材需要は、このロシア極東の森に支えられてきたのだ。

【写真8】猟師小屋でアカシカを調理するウデへの人
このほかアカシカやイノシシは食用に、チョウセンニンジンやエゾウコギは薬剤原料になる。ヌタ場や水場に来るアカシカを待ち伏せする猟や、森に生える薬草の効能など、森の民・ウデへのハンターから次々と森と生きる術が披露された。
若手ハンターのワーニャさん(29)は、11歳の頃、たった一人で200kg級のシカを仕留め、一人前のハンターになったそうだ。「タイガの森とは、あなたにとって何か」、そう尋ねると、「タイガは肉と魚を与えてくれ、いずれは自分の子どもも食わせてくれる。崇拝する対象だ」。いつも冗談ばかり言うワーニャさんが、この時だけは、そう真顔で語った。
タイガがなくなることは、私たちがなくなること。
ロシアでは土地や森林は国のものであり、地方政府が大手企業に長期伐採権を供与するケースが、ここビキン川流域でも毎年のように起こっている。そのたびにこの村の人々は立ち上がり、伐採業者らと戦い続けてきた。一方、旧ソ連崩壊で生活が苦しくなる中、やむを得ず、森林伐採を受け入れた先住民族のケースも少なくない。

【写真9】元村長のアレクセイ・ウザさん=村役場の前で
この村の生活が楽というわけでもないようだ。元村長のアレクセイ・ウザさんは、「道路が舗装されていないせいで、輸送コストが余計にかかる。だから品物は何でも高い。けれども道路を舗装するお金がない」と嘆く。隣町からの送電用ケーブルも整備したいし、ゴミ処理場や下水処理場もつくりたい。「お金さえあれば、問題は解決できるのに」と、ウザさんは繰り返す。
「お金を稼ぐ最も手っ取り早い方法は、木の伐採だ。木を切らないので、村にはお金がない」。そう語るウザさんに、ではそもそも木を切らないのはなぜか、と敢えて尋ねた。するとウザさんは「タイガがなくなることは、私たちがなくなること。1950年代、タイガを伐採したウデへは、森もウデへもなくなった」と答えた。
ウデへの人々はいま、タイガの森をなくさないために、世界遺産登録を目指して活動を進めている。
