Image may be NSFW.
Clik here to view. 取材・写真・文/大草芳江
取材・写真・文/大草芳江
2012年8月18日公開
~「教育って、そもそもなんだろう?」を探るべく、【教育】に関する様々な人々をインタビュー~
仙台二高・仙台一高の文化祭実行委員会から、
「宮城の新聞」への取材依頼が今年も舞い込んだ。
各校で開催する文化祭の宣伝合戦をしたいのだと言う。
文化祭は、生徒達が日頃の学習成果を総合的に生かす場であり、
校風を肌身で感じたり、今後の方向性を垣間見ることができる好機でもある。
古くより良きライバルとして切磋琢磨してきた両校。
そもそも高校生の彼らは一体何にリアリティを感じて活動しているのだろうか。
彼らの原動力やスタンスなどのインタビュー取材を通じて、
文化祭の舞台裏から見える、仙台一高生・仙台二高生の「今」を探った。
【リンク】
仙台一高「壱高祭」(9月1日~3日)
仙台二高「北陵祭」(8月31日~9月2日)
【関連記事】
・特集:文化祭から見える高校の「今」(2008年:宮城二女、仙台一高、仙台二高、宮城一高)
Clik here to view.
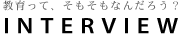
仙台一高「壱高祭」・仙台二高「北陵祭」実行委員会の皆さんに聞く
Image may be NSFW.
Clik here to view.
■仙台二高「北陵祭」実行委員会(左側、手前から):
・実行委員長の針生明日可くん(3年生)
・企画局長の本橋優香さん(3年生)
・広報局長(記念品製作部長)の遠藤夏実さん(3年生)
・会場局長(施設警備部長)の阿部紘平くん(3年生)
・事務局長(庶務部)の加々美望くん(3年生)
●仙台一高「壱高祭」実行委員会(右側、手前から):
・実行委員長の後藤颯太くん(3年生)
・宣伝広報部長の松川咲子さん(2年生)
私が文化祭実行委員である理由
―まず、なぜ皆さんは文化祭実行委員になろうと思ったのですか?
きっかけや、続けているモチベーションについてお話ください。
では、最初に取材依頼をしていただいた、仙台二高さんから。
■実行委員長の針生くん(二高):
「楽しみながらやる雰囲気に惹かれて」
きっかけは、北実(北陵祭実行委員)の先輩たちの宣伝や勧誘です。
1年生の時、北実の先輩たちの雰囲気が良く、楽しそうと思ったので、
2年生でも本部員になりました。そして、いつの間にか委員長に(笑)
先生方からは「文化祭も授業の一環だからな」と釘を刺されますが(笑)、
節度を守りつつ、皆でわいわいと楽しみながらやっていきたいですね。
■企画局長の本橋さん(二高):
「自分の納得がいくものをつくりたい」
私は2年生の時の北陵祭が自分の納得できるものではありませんでした。
「これじゃあ駄目だ。もう一年頑張ろう」と思い、今年も続けています。
北陵祭をどのようにしていくのか、自分は何のために仕事をやるのか。
そういったこともきちんと考え、北陵祭の雰囲気づくりに貢献したいです。
■広報局長の遠藤さん(二高):
「先輩たちを超えるものをつくりたい」
オープンスクールの説明会で、北実の先輩たちの思いや考えを聞きました。
自分が二高に入れたら、絶対に先輩たちを超えるようなものをつくりたい。
そう思って、二高に入ろうと決めたのです。
1年生で北実に入れるのは、クラスで5人だけ。倍率は約3倍でしたが、
じゃんけんで勝って入れました。2年に上がる時は有志なので残りました。
先輩たちができなかったことを超えられるように、やっていきたいです。
■会場局長の阿部くん(二高):
「皆で一つのことをつくるのが楽しい」
北祭の先輩たちの勧誘で、単純に「おもしろそう」と思ったことと、
昔から、裏方の仕事に興味があったことが、最初のきっかけです。
その後、続けている理由は、自分でもよくわかりません。
でも、皆で一つのものをつくっていくことが単純に楽しいから、
これまで続けてきたのかなと思います。
■事務局長の加々美くん(二高):
「やり遂げる達成感を味わいたい」
最初のきっかけは、応援団委員に入るのが嫌だったので(笑)、
実行委員に入ったという、ちょっとマイナスな理由でした。
2年生でも続けて達成感を味わい、3年生で事務局長になりました。
事務局長の仕事は、お金を管理することです。
それが、びっくりするくらい大きなお金なので、
しっかりと管理して、やり遂げたいですね。
―それでは次に、仙台一高さん、お願いします。
●実行委員長の後藤くん(一高):
「一生の仲間と社会に通じる力を培う」
壱高祭実行委員会は完全有志です。4月末の説明会に誘われて行って、
「楽しそう」と思って入りました。最初は些細なきっかけだったのです。
二高さんの場合は、3年生が中心になって仕事をするようですが、
一高の場合、2年生が中心となって、ほとんどの仕事をします。
その下に1年生がいて、3年生は「アドバイザー」の立場です。
1年生の時、仕事を通じて、中学校の文化祭との違いを感じました。
まず仕事量が全然違います。でも2年生の先輩たちは、仕事がすごく
大変な中で雰囲気がとても良く、自分もやりがいを感じました。
2年生になって、「自分はなぜこんなことをしているのだろう?」と
思うくらい大変な仕事をしました。遅い時は夜8時まで仕事をしたり。
それが、4月から8月までずっと続きます。
そんな一杯一杯な状況の中、チームワークを発揮して仕事をやり遂げ、
大きな達成感を味わいました。一生離れない友達ができたと思えました。
また、実行委員の仕事は、例えば今回のように新聞取材を受けることも、
先生を通さず、生徒だけですべてやります。これは社会にも通じること。
その積み重ねにより、社会に通じるものが培われていくと思います。
つまり、仲間といった熱い感情的な面もあれば、
社会に役立つ力といった実用的な面も、身に付けることができます。
3年生では、「壱高祭を見届けたい。そのために委員長になろう」と
思って残りました。委員長には、実務的な仕事がほとんどありません。
実行委員全員が集まる会で、俺は委員長として、どんな委員会をつくり、
どんな文化祭にしたいのか。委員長としての考えを反映させる仕事です。
それを絶対にやってやる、去年を超えてやる。そう思って今に至ります。
●宣伝広報部長の松川さん(一高):
「先輩たちの本気に触れて」
1年生の時は「楽しそう」と思って入りましたが、
去年は1年生だけで60人近い委員がいたこともあって、
それほど仕事をできた実感がなく、自分自身に反省点も多くありました。
ところが、いざ壱高祭を迎えると、先輩たちの本気度が全然違うのです。
最終日直後に全員で話し合った時、先輩たちの思いを聞いているうちに、
「私も先輩たちのようにつくってみたい。先輩たちができなかったことを、
できるようにしたい」と強く思いました。それを今も続けています。
何より達成感があって、それが心地良かったのです。
その達成感を味わいたい気持ちもあって、今も続けていると思います。
「壱高祭」と「北陵祭」
―皆さんが、文化祭実行委員のどのようなところに価値を見出して、
何を原動力にしているか、それぞれ伝わってきた感じがしました。
では次に、今年の文化祭のテーマについて、教えてください。
●宣伝広報部長の松川さん(一高):
「非日常への誘い」
Clik here to view.

今年の壱高祭テーマは「非日常への誘い」
今年の壱高祭テーマは、「非日常への誘い」です。
昔から「一高の常識は世間の非常識」と言われますが(笑)
ディズニーランドが入った瞬間から「夢の国」であるように、
壱高祭も入った瞬間から日常を忘れて楽しんでもらえる、
テーマパークのようなお祭りにしたいと考えています。
それも、お客さんに来てもらわないことには始まりません。
いろいろな人に、壱高祭の存在や、その良さを知ってもらい、
たくさんのお客さんに楽しんでもらいたいと考えています。
■事務局長の加々美くん(二高):
「REVOLUTION 北陵ノ変 2012」
Clik here to view.

今年の北陵祭テーマは「REVOLUTION 北陵ノ変 2012」
今年の北陵祭テーマは、「REVOLUTION 北陵ノ変 2012」。
二高から革命の意識を発信していこうと提案したものです。
実行委員会の中では、前年の反省を革新していこう、
という共通意識があります。
また社会に対しては、東日本大震災の復興にむかって前に進む
すべての人を応援したい、という思いも込めています。
―では次に、それぞれお互いに自分の高校が独自だと思う取組みや、
逆に、他校ではどうしているのか、質問したいことはありますか?
それを通して、各校の文化祭の特徴を知りたいと思います。
■事務局長の加々美くん(二高):
二高では、記念品グッズ販売のほか、チャリティーバザーも行います。
グッズ販売以外に、実行委員会主催でやっているお店はありますか?
●広報宣伝部長の松川さん(一高):
バザーはないですが、去年から新企画「茶畑大抽選会」があります。
一高では、部活動ごとに出店しています。
そこで50円購入ごとにもらえる赤いシールを
10個ためると、くじ引きで景品がもらえます。
どんな景品かは当日のお楽しみ。秘密グッズもあります。
去年なかなか好評でした。
一高では、壱高祭開催後に「活性化委員会」をつくり、
来年にむけて、実行委員が一人ひとつ以上、企画を練ります。
茶畑大抽選会も、その一つとして先輩が出した案。
提案した企画はアドバイサーの先輩に見てもらい、
承認いただいたら、壱高祭の企画として実施されます。
Clik here to view.

壱高祭名物・水泳部によるウォーターボーイズ(写真は2008年取材時)
ですから実行委員会の企画はステージと夜祭と福引。
ほかは、有志による企画で、各団体に任せています。
その中で最も有名なのが水泳部の「ウォーターボーイズ」。
今年は水泳部の大会と重なり、3日目限定となりますが、
逆に言えば、3日目は必見です!(笑)
■実行委員長の針生くん(二高):
二高では、実行委員会による企画は、バザーと講堂で行う夜祭です。
新企画にビンゴ形式のスタンプラリー「ウォークラリー」もあります。
ほかは、各部活に任せて展示をやってもらいます。
基本的に自由ですね。
例えば、かき氷や綿飴など、お祭り的な要素もあれば、
化学部・物理部・地学部・生物部の理科棟連合によるピタゴラスイッチ、
地学部によるプラネタリウムなど、二高ならではの文化的な出店もあります。
●実行委員長の後藤くん(一高):
一高でも、物理部がロケットを校庭で飛ばします。
「今からロケットを飛ばします」と校内放送がありますよ。
一高の夜祭は、1日目が「初夜祭」。
一高生の持つポテンシャルすべてを出して、下ネタなし(笑)。
2日目の「中夜祭」は、ちょっとアダルティな内容を(笑)、
初夜祭とは違った内容でやります。
すべて一高生が出演者。他の展示もなく夜祭に集中するので、
お客さんも生徒も夜祭を全部、見ることができます。
■会場局長の阿部くん(二高):
Image may be NSFW.
Clik here to view. 二高では、モニュメントの題材を決めて、
二高では、モニュメントの題材を決めて、
木材を発注してつくるまで全部、生徒側でやります。
今年のモニュメントは、テーマ「REVOLUTION~北陵ノ変」
に沿って、改革の思いを込め、ナポレオンにします。
一高にもモニュメント的なものはありますか?
●実行委員長の後藤くん(一高):
Image may be NSFW.
Clik here to view. 一高では、テーマに沿って、デザインを施した、
一高では、テーマに沿って、デザインを施した、
木製のゲートをつくります。
ほかに見世物としては、HR(ホームルーム)ごとに壁画を
つくって展示します。ですから、一般生徒の参加は、
HRの壁画と、部活としての出店です。
北陵祭はクラス出店が多いんですよね?
■実行委員長の針生くん(二高):
二高ではクラス出店が多く、1年生はほとんどのクラスが出店します。
部活でも出店するので、ローテンションを組んで部活と両立しています。
文化祭実行委員会がそれぞれのクラスへ説明に行くと、
クラスの中心的な人が出て、「やるぞ」となる場合が多いですね。
食べ物関係が多いですが、射的やミニゲーム、お化け屋敷など。
フィーリングカップル的なものとか。お祭り的要素が多いですね。
●実行委員長の後藤くん(一高):
お化け屋敷は、一高も凄いですよ。
「女子とカップルのみ入場可」みたいな(笑)
あとは、人間もぐらたたきとか、パイ投げとか。
■実行委員長の針生くん(二高):
パイ投げは、二高では今年、却下されましたね(笑)
●実行委員長の後藤くん(一高):
新しく出た企画は審査がありますし、
食品関係は検便の義務がありますが、
伝統的にやっているものは多めに見ていますね。
男子校時代からずっとあるものなので。
■実行委員長の針生くん(二高):
二高では、企画が毎年どんどん変わるので、毎年審査をします。
危険なもの以外はだいたいOKですが、「ちょっと際どい...」ものは、
参加団体受付部長が、文化祭顧問と協議して審査します。
●実行委員長の後藤くん(一高):
一高よりも二高の方が、部局が細かく分かれているみたいですね。
そのメリットとデメリットは何ですか?
細部に分かれていると、当日困ったりはしませんか?
お客さんに質問された時の対応とかは?
■実行委員長の針生くん(二高):
メリットは、仕事が具体化しているので、
本部員の負担が少ない点ですね。
まとまって全体を動かそうとすると負担が大きいですが、
一般部員には明確な仕事があるので、それぞれ割り振った仕事を
着実にしてくれれば、本部員の負担が少なくなります。
一般部員には本部員が研修会で「こんな時はこうして」と説明します。
当日、判断できない場合は「トランシーバーで本部にすぐに連絡しろ」と言います。
一方、デメリットとしては、もし当日に来ない一般部員がいると、
仕事がエキスパート化されているので、そのカバーが大変ですね。
●実行委員長の後藤くん(一高):
そういう意味では、一高には、逆のメリット・デメリットがあるかも。
一高には5部署しかないので、部署内の仕事は全員わかっている状態です。
2年生は他の部署の仕事もよくわかっていて、当日も柔軟に対応できます。
でも逆に言えば、部署あたりの負担も大きいというデメリットもあるかな。
文化祭の「舞台裏」にあるもの
―実行委員会の体制に、学校のスタンスが現れているようで、大変興味深いですね。
そのような文化祭ができる「裏舞台」には、皆さんがそれぞれ役目役割を果たしつつ、
主体的に活動する原動力や意思があって、一つの文化祭ができるのだと思います。
それぞれの立場で、最も力を注いだ点や、苦労した点は何ですか?
■企画局長の本橋さん(二高):
「珠玉混合の案を柔軟に取り入れるのに苦心」
企画局は、如何に企画でお客さんを楽しませることができるかに
かかっています。ですから、そこを一番の目標にしています。
そのためには、お客さんに参加してもらうことが一番と考えました。
そこで今年は、「BAD LUCK~不幸を祈る~」を新しく企画しました。
いくつかの運試しをしながら、一番運のない一人を決めるものです。
不運と言っても悪いわけでなく、笑いありスリルありで盛り上げます。
まさに、お客さんを楽しませることだけを目的に考えた企画ですので、
ぜひ多くの方にご参加いただきたいです。
また今年は、北陵祭をより楽しんでいただくために、
ビンゴ形式のスタンプラリーをパンフレットに載せました。
ビンゴがそろうと、景品と引き換えができますので、
ぜひ、いろいろな出店をまわってみてください。
―そのような企画をつくる中でどんな点に苦労しましたか?
また、その苦労をどのようにして克服しましたか?
我々企画局が企画に最も詳しいことや、過去の前例にとらわれずに、
企画局以外の本部員の案も、柔軟に取り入れていくことが難しかったです。
どんな企画にも、良い点と悪い点があるのは、付物ですからね。
そこで私が重視したのは、歴代の引継資料です。
引継資料を読み漁り、去年までの良かった点・反省点を参考にしながら、
アイディアを判断していきました。
けれども、昨年は「前例」が良くない方向に働いて、
「前例があるからいいじゃん」と考えも凝り固まっていました。
だからこそ今年は、企画局だけでなく本部員のアイディアも広く
柔軟に取り入れ、より良い企画をつくっていこうと思ったのです。
■広報局長の遠藤さん(二高):
「企業広告を1から全部考えた」
Clik here to view.

今年の広報局長の仕事は、主に企業広告でしたが、
大変苦労しました。二高では、企業広告を5年前から
去年まで行なっていなかったので、5年前の資料も
ほぼ残っておらず、1から考える必要がありました。
まず自分たちで企画書をつくった後、いろいろな人の意見を聞きました。
企業広告を行う他校からも話を聞き、参考にしながら組み立てました。
企業に電話をかけても、断られることや、キツいことも言われました。
30件中2件しか取れなくて、「目標に届かないかも」と焦りました。
でも、やっているうちに、不足点などにも気づくようになり、
少しずつ、柔軟に対応できるようになっていきました。
新しいことを始めることは、いつもより道のりが長いと感じましたが、
結果的には目標を超す数が集まり、自分は強くなったと感じています。
記念品製作部長としては、制作物にミスがないよう気をつけつつ、日々、
締切日に追わました。ミスもありましたが、過ぎたことは仕方ないです。
逆に、自分のミスを後輩たちに上手く引き継ぐことで、後輩たちには、
新しいミスはあっても、同じミスは繰り返して欲しくないですね。
■会場局長の阿部くん(二高):
「安全のために常識から考える」
会場局では、安全面やスムーズな入退場を心がけています。
Clik here to view.

「北陵祭」カウントダウンボード
会場局は、校舎内の装飾を行う「装飾整備部」と、
校舎内の警備・巡回を行う「施設警備部」、
モニュメントの設置をする「モニュメント部」。
この3つに分かれます。
装飾整備部は、人がひっかかって転んだりしないよう、
安全面を考慮しつつ、同時に、最大限の華やかさを
出していくことが大変だと感じています。
モニュメントは、高さ4メートルもあります。
建築のノウハウも無い中、技師さん2人と「こう組めば安全で強度が出る」
「こんな装飾をしたいが大丈夫か」と、何度も話し合いながら製作中です。
完成までこぎつけるのが、大変なところです。
施設警備部の仕事は、警備とゴミの管理です。
ゴミが溢れたりしていないか、問題が起こってないか、巡回します。
会場は混雑しているので、参加者同士で問題が起こらないよう、
駐輪場の設置場所や誘導方法などをどうすべきか、頭を悩ませます。
―「こうすれば安全」という基準をつくること自体が簡単ではない、
と思いますが、それはどのようにしてつくっているのですか?
僕達が一番大事にしているのは、常識から見ていくことです。
プロの警備会社なら、予め視点が用意されていると思いますが、
それがない僕達は、当前のことが当前に行われているかどうか?
という視点が、安全に運営する上で大切なことだと思います。
例えば、駐輪場で自転車が通るには60cm幅がなければ通れません。
ですから、出店団体が60cm幅を空けずに宣伝していないか?
などを巡回で見ています。
ただ、いくら頭で考えていても、予想しない事態は起こるものです。
でも予め頭で考えていなければ、想定外のことが起っても動けません。
ですから「こんな場所なら、こんな問題が起こるだろう」と
様々なパターンを考えて、さらに資料に残したりしています。
■事務局長の加々美くん(二高):
「お金の管理はシンプルだけど重要」
お金の管理が、主な仕事です。その仕事内容はシンプルですが、
北陵祭にとって重要なことであることは、常に意識しています。
予算と支出・収入が合わなかったりすると、破綻しますから。
ただ、急に買い足す必要がある時など、最初の予算金額が変わって
混乱することもあるので、出納帳に詳細に書くよう心がけています。
また、企業広告については、今までのノウハウがなかったので、
いろいろ失敗したこともありました。
だからこそ、来年の後輩につなげようという意識を持っています。
―続いて、仙台一高さん、お願いします。
●宣伝広報部長の松川さん(一高):
「『高校生だから』は通用しない」
Clik here to view.

他の部長が来れなかったので、私から説明しますね。
一高の場合は、総務部・会場部・夜祭部・ステージ部
・宣伝広報部の5部署があります。
夜祭部・ステージ部は、一つのエンターテインメントとして、
舞台を如何に盛り上げ、お客さんに楽しんでいただけるか
を目指し、下準備やリハーサルを重ねて頑張っています。
会場部は、いろいろな装飾をつくりつつ、
当日の実行委員の流れを考えて人を配置する部署です。
特に今年は去年より実行委員の人数が少ない中、如何にスムーズな流れを
つくり、お客さんに不便を感じさせず楽しんでもらえるか、考えています。
そして、私がいる宣伝広報部は、ポスターやパンフレットの作成のほか、
広告取りやメディアへのアポイントなどが主な仕事です。
今年新たな試みとして、開催2週間前からJR仙台駅のエレベーターで
壱高祭のアドビジョン広告を出します。皆さん、ぜひ見てください!
1万人来場を目指して、いろいろな人に知ってもらうためには
どうすればいいかを考えることが、大変でもあり、楽しいことです。
―宣伝広報部としての苦労や、力を入れている点は何ですか?
宣伝広報部は、企業や社会人の方とも関わる仕事です。
そこが、やっぱり中学校とは全然違います。
自分と全くつながりのない方にお願いする仕事ですから、
失礼のないようにすることが大事で、社会で通用する力が必要です。
「高校生だから、しょうがないね」というのは、嫌なんです。
お金をもらう仕事ですから、社会に出ているのと同じ。
「高校生だから」という言い訳は、通用しません。
少しずつではありますが、
社会で通用する力を身につけられているのかな、と思っています。
●実行委員長の後藤くん(一高):
「事務的な仕事が無ければ、壱高祭が開催できない」
2年生の時、僕は総務部にいたので、僕から総務部について説明します。
総務部の仕事は主に事務的なことですが、逆に言えば、
総務部の仕事が無ければ、壱高祭自体が開催できません。
例えば、先生方の会議で壱高祭の方針や報告を伝える資料を作成したり、
グッズデザイン、ファイヤーストームの管理なども総務部が行います。
先生方の協力も不可欠ですから、先生方との協議も、総務部が行います。
許可や承認を得るための申請資料も、すべて総務部が作成しますが、
一つでもミスがあれば、実行委員会が動けなくなってしまいます。
その責任の重さが、肉体的にも精神的にも大変でした。
このように総務部の仕事をこなすことが、壱高祭をスムーズに
開催できることにつながることを、常に心がけていました。
●宣伝広報部長の松川さん(一高):
「女子生徒の活動も見て欲しい」
Clik here to view.

「壱高祭」カウントダウンボード
そして一高は今年、創立120周年、壱高祭は55回目、
男女共学化完全完了という一つの節目を迎えます。
「男子校時代の方が良かった」という意見もきっとあるでしょう。
それも、一つの考えとして受け入れるのが、一高生です。
けれども「女子が入って壱高祭がおもしろくなくなった」とは、
絶対に言われたくない。ずっと私はそう思っていました。
男子校独自の雰囲気がなくなるのは事実なので仕方がありません。
けれども、男女共学になったからこその魅力もあると思うのです。
今の一高は半数以上が女子で、男女の仲が悪いわけでもありません。
皆一緒に頑張っています。そんな女子の姿もぜひ見てもらいたいです。
実行委員長としての思い
―それでは、実行委員長のお二人は、それぞれ実行委員長として、
どのようなことに力を注ぎ、そして苦労していますか?
●実行委員長の後藤くん(一高):
「自分の意志で仕事をしてほしい」
俺が直接、実行委員に指示を出したり概念を言える集会の時、
その場で皆に何を話すか、いつも考えています。
そこで意識しているのは、全員が楽しんで仕事ができる流れにすること。
何より、自分の意志を持って仕事をすることを最重視して、強調します。
自分の意思で考えて、自分がやりたいことを突き通す実行力と、
なおかつ楽しんでやれるシステムを、ぜひ整えて欲しいのです。
気持ちを伝えることが、委員長の一番の仕事だと考えています。
けれども、その概念をわかってもらうことが、一番大変ですね。
言葉を試行錯誤したり、自分の行動として見せたりしながら、
概念の伝え方を、日々考えています。
―「自分の意志を持って仕事をすることを最重視」するのはなぜですか?
アドバイザーがいるので、聞けばわかります。
けれども、そうやって機械的に仕事をするのでは、
自分の経験上、達成感は得られないと考えるからです。
一高には5部署しかないので、ある程度、自由な考えが認められています。
逆に言えば、休もうと思えば休めるし、強制もされません。
だからこそ自分の意志で関わっていかないと、
「全然仕事しないで終わったな」と、何となくで終わってしまう。
そんな後悔は残してほしくないのです。
だから2年生には、「自分の意思を仕事に反映させて、
自ら積極的に関わって欲しい」と、いつも話をしています。
けれども、押し付けがましいのは駄目。
先生と後輩の意見も踏まえて、委員長としての公的な発言をする。
そのような姿勢に、だんだん今まで変わっていきました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
■実行委員長の針生くん(二高):
「伝統的に積み重ねていく組織」
委員長としての仕事は、具体的な業務があるわけではなく、
全体の仕事を把握して、各委員に指示を出すことです。
僕は、そのための雰囲気づくりを心がけています。
自分の中では、「楽しくやろう」というのがあります。
文化祭を実行する側が楽しまないと良いものにならないので、
実行委員も楽しくやれる雰囲気をつくろうとしています。
けれども、実行委員会だけの自己満足だけで終わらず、
まわりも楽しませていくことを大切にしたいです。
そのためには、一高さんとは違って、僕は集会の時、
自分からはあまり話さずに、2年生に話をさせます。
それぞれの実行委員がどんな意見を持っているか、
全体にわからせることをやっているのです。
その前提として、自分がつくる雰囲気に自分の考えを反映させれば、
一人ひとりにあえて言う必要はない、と考えています。
個々人のモチベーションや意識は本部員が集まる中で高めていきます。
二高は組織化されて機械的な動きをする委員会ですが、
その中でも、個を重視しているのです。
個々人が改善したいことを見つけられる雰囲気をつくりたいと思っています。
北陵祭実行委員は、伝統的にOBの雰囲気が受け継がれています。
一高さんでは、一代ごとに変わるかもしれませんが、
二高は、一回ごとに切り替えていく組織ではなく、
積み重ねていく組織なのです。
ですから、より良いものをつくるために、引継を重視します。
3年生引退後も、2年生にきちんと残してやりたい。
引き継ぐ中でも、我々3年生の姿を見て、後輩たちが
考えたことや感じたことを、ぜひ引き継いでもらいたい。
また、自分も企業広告のために企業まわりを手伝いましたが、
「高校生だから」という扱いはされなくて、むしろ企業側から、
「自分たちにどんなメリットがあるか説明せよ」と言われました。
集団の中の利害関係のつながりが見え、我々も例外ではないのだな、
と感じられました。そのようなことも社会で役立つと感じています。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
―両校それぞれのスタンスが伝わってくる、大変興味深いお話でした。
スタンスや方法論はそれぞれ異なりますが、より良いものを目指していこう、
という思いは共通だと感じられました。では最後に、両校の実行委員長から、
来場者にむけてメッセージをお願いします。
●実行委員長の後藤くん(一高):
壱高祭に来てもらった方には、
ぜひ一高独特のユニークな雰囲気を感じてもらいたいですね。
そのために壱高祭では、一高でしかやれないことを心がけて、
一つひとつやっています。
一高にしかないものを見て、一高の性格を知ってもらいたい。
そして、皆さんに楽しんで帰ってもらいたいです。
■実行委員長の針生くん(二高):
二高・一高と言うと、イコール「頭が良い」イメージだけで
終わってしまうけど、勉強だけじゃないんです。
楽しむところは楽しむし、社会に出た時に役立つ高校だと知ってもらいたい。
ぜひ多くの方に来てもらって、楽しんでもらいたいです。
―皆さん、本日は長い時間、ありがとうございました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
座談会後の一コマ。お互いの活動に興味津々なようで、その後も意見交換されていた実行委員会の皆さん。
「スタンスは違えど、お互い認め合っているんです」とお話されていたことが印象的でした。
